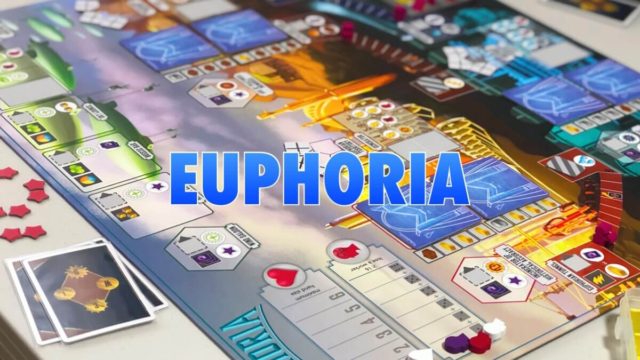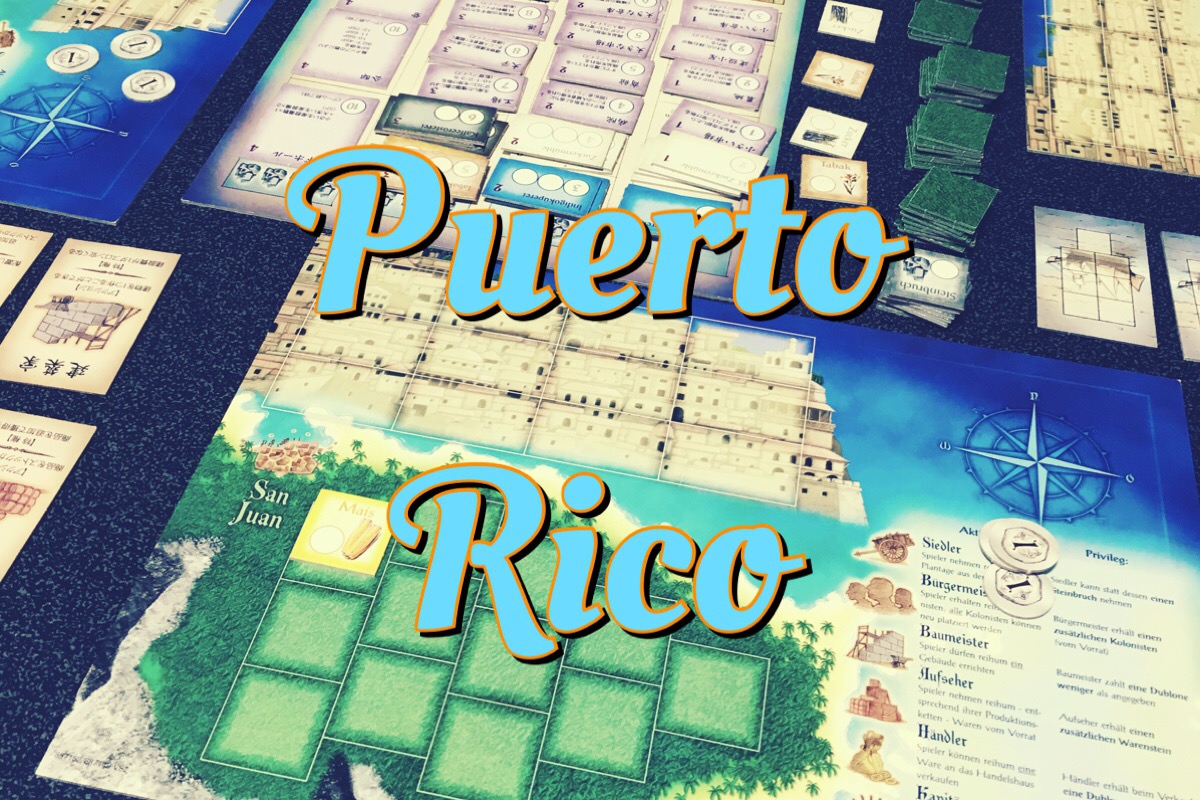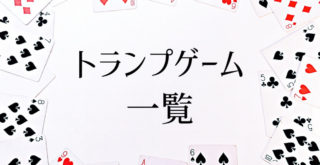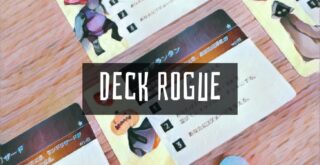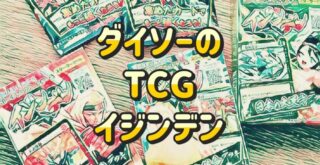GIPFはベルギーのKris Burm による2人用アブストラクトゲームシリーズ、Project GIPFの最初の作品です。シリーズの名前に含まれていることから分かるように、このシリーズの中核ともいえる作品です。
そもそもアブストラクトゲームとは?
いろいろなボードゲームを遊んでいると「これは完全にアブストラクトだ」「ちょっとアブストラクトっぽい」といった言葉を耳にすることがあります。また「運要素がない=アブストラクト」というイメージを持たれている人も多いのではないでしょうか。
アブストラクトゲーム (Abstract Games) とは、ゲームの分類の1つで、広義には名前通り抽象的(アブストラクト)で、元となった現実の出来事(テーマ)などとゲームの内容とが余り関係のないものになっているゲーム、あるいは具体的なテーマが全く存在しないゲームを指す。(Wikipedia)
簡単にいうとゲームとしての具体的なテーマがないようなものがアブストラクトゲームです。
たとえば、オセロやマンカラ、五目並べといったものはコマ自体に意味がないので、アブストラクトゲームです。それに対して将棋やチェスなどはコマに設定があり、それぞれ異なる能力があるため、厳密にはアブストラクトゲームには含まれません。
ただし、最近はそこまで厳密な意味合いを持たせていないことがあり、運要素がなく、すべての情報が公開されているものをアブストラクトゲームと呼ぶことが多いです。
GIPFについて
GIPFには黒と白のコマがあり、プレイヤーはどちらかの色を担当します。
ゲームボードには24個の始点(黒丸の点)と37個の交点があります。コマは始点からスタートし、線に沿って、交点上を移動します。
GIPFには基本を学ぶためのベーシック、本来の遊び方であるスタンダードの2つのルールが用意されています。
ここでは基本のベーシックルールを説明します。
手番ではボード上の始点のいずれかにコマを置き、そこから線にそって1つ先まで移動させます。移動先にコマがあれば、そのコマも一緒にすべてを1つずつずらしていきます。ただし、ゲームボード外に押し出すことはできないため、そういった場合は配置することはできません。
コマを移動させたときに同じ色のコマが4つ一列に並んだら、そのコマすべてがボードから外されて手元に戻ります。その一列に相手のコマがあれば、それはゲームから取り除かれます。
たとえば、移動させた結果○○○○●○●となれば、○は手元に戻り、●はゲームから除外されます。
これを一手番ずつ繰り返し、配置できるコマがなくなった方の負けです。
情報量が多い四目並べ
すべきことは始点に配置、1歩移動だけなのですが、考えるべきことはかなり多いです。一手番でその列のコマすべてが動くため、先を考えた手を打たなければなりません。当然相手がどういった手を打つかも同時に考えなければなりません。
今回はベーシックルールで遊んだのですが、スタンダードではGIPFというコマが加わり、さらに考えるべきことが増えます。(ベーシックでは4つ並ぶと同じ色すべてが戻るのですが、GIPFは戻るか残すかを選ぶことができます)
ベーシックで1回遊んでみた感想は「ちょっと情報の処理が間に合わない」といった感じでした。
初回ということもあり、どう動かせばいいのかも分からないまま、少しずつコマが減っていく感じで、中盤から「あ、これ無理だ」と悟りました。打つ手打つ手が裏目にでて、結構な差で敗北しました。
この手のゲームは回数をこなして見えてくる部分が多いと思います。
そのため、2人で数をこなせるような環境にあればお勧めできますが、ちょっと2人で1回だけ遊んでみる、といったケースではあまりお勧めできません。時間も1プレイ45分ほどと結構かかりました。
GIPFプロジェクトは現在7作品あります。
それぞれ2人用のアブストラクトなのですが、プレイ感は結構違います。また、遊んだ人によって好みの差が大きいところが興味深いです。Twitter上で好きな順番を挙げるタグがあったのですが、見事なまでにバラバラでした。そのため、これからどれかを買おうという人はとても困るはずです(笑)
買う前にどこかで遊べる機会があれば、一通り遊んでみるのがお勧めですね。
実力差がはっきり出るので、合わない人は間違いなく合わないとも思います。