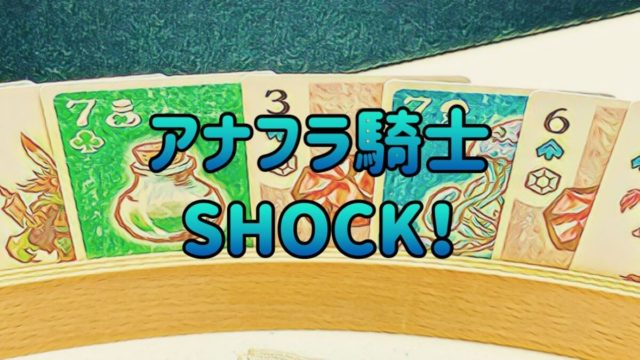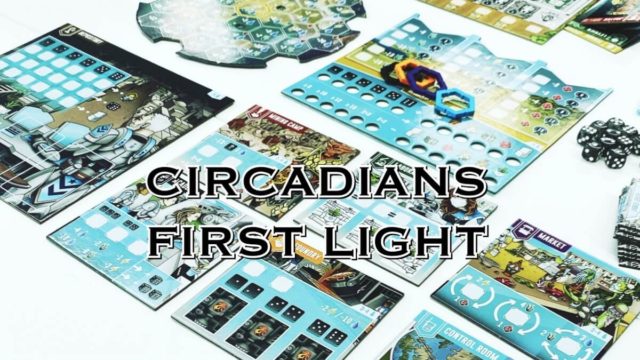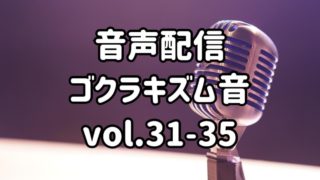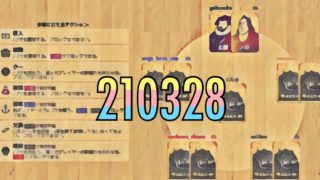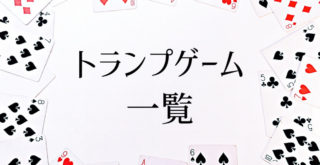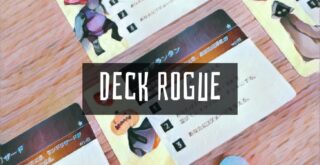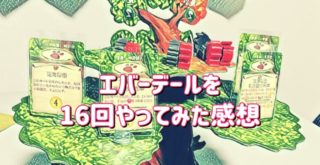レースフォーザギャラクシーは、さまざまなカードをプレイして自分の銀河国家を建立する2~4人用のゲームです。2007年発売のゲームですが、2021年に第2版の日本語版が発売されました。
レース・フォー・ザ・ギャラクシーについて

準備
プレイヤー人数×12VPの勝利ポイントチップを用意します。
各プレイヤーはアクションカード(一色)7枚を受け取ります。
その後、右下に数字が入った初期ワールドカードを1枚ずつ配ります。このカードは、各プレイヤーのカード置き場に表で置かれます。
ゲームカードをシャッフルし6枚ずつ配ります。そこから4枚を選んで手札とし、残りは捨てます。
ゲームの進行
ラウンド開始時、各プレイヤーはアクションカードの中から1枚を選び、一斉に公開します。アクションカードにはⅠ~Ⅴのフェイズのいずれかが書かれています。
Ⅰから順番に行っていきますが、誰も選ばなかったフェイズは飛ばされます。
誰かが選んだフェイズは全員が行いますが、選んだプレイヤーにはボーナスがあります。
Ⅰ:探査
全員:カードを2枚引き、1枚を手札に、もう1枚を捨てます。
ボーナス:カードを引く枚数が5枚増えます。
ボーナス:引く枚数が1枚増えて、手札に残せる枚数が1枚増えます。
Ⅱ:発展
全員:コストを支払い、デベロップカード(菱形)を1枚プレイします。
ボーナス:コストが1軽減します。
Ⅲ:移住
全員:ワールドカード(丸形)を1枚プレイします。
黒字:コスト分の手札を捨てます。
赤字:その分だけの軍事力を持っている必要があります。手札を捨てる必要はありません。
プレイしたカードが単発生産ワールド(丸の外側に色がついている)ならば、製品を置きます。生産ワールド(丸の中が塗りつぶされている)には置きません。
ボーナス:ワールドカードをプレイできたら、カードを1枚引きます。
Ⅳ:消費
全員:プレイしたカードに書かれたⅣの効果を使い、製品を勝利ポイントやカードに変えます。
ボーナス:消費する前に製品1つを売却し、色に応じた枚数のカードを引きます。
ボーナス:消費によって得られる勝利ポイントが2倍になります。
Ⅴ:生産
全員:生産ワールドに1枚ずつ製品を置きます。
ボーナス:単発生産ワールド1つに製品を置きます。
ラウンドの終了
手札が10枚を越えていれば、10枚になるように捨てます。
先ほど使ったアクションカードを戻します。
ゲームの終了
ラウンド終了時、以下のどちらかの条件を満たしていればゲーム終了です。
- 誰かが12枚以上カードをプレイした。
- 勝利ポイントチップがなくなった。
最終得点計算を行い、もっとも勝利点が多いプレイヤーの勝利です。
カードを追加・調整して復活
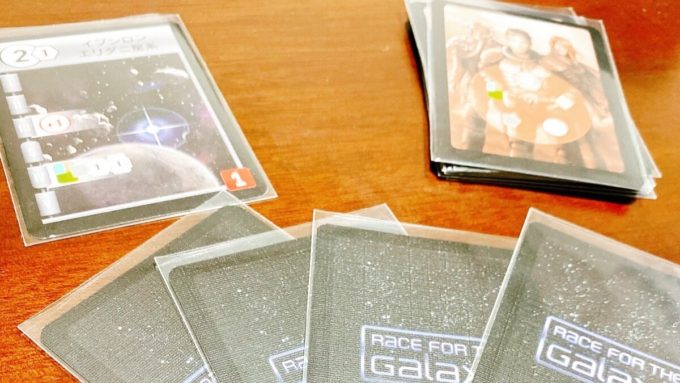
2007年発売のゲームで、2010年に日本語版が発売されました。今年発売された第2版では、いくつかのカードが調整され、新たな初期ワールドが加わっています。
裏面のデザインは変わっていないようなので、第2版でも拡張セットは以前のものがそのまま使えるようです。現在、「嵐の予兆」「帝国対反乱軍」「戦争の影」という3つの拡張セットの日本語版が発売されています。
プエルトリコをカードゲーム化したサンファンがありますが、レース・フォー・ザ・ギャラクシーはサンファンとシステムが似ていたため「宇宙サンファン」などとも呼ばれていました。
ただ、実際にやってみるとサンファンよりもだいぶ複雑です。
アイコンの数が多く、カードによってコストが異なり、消費の方法もいくつかあるため、初回はかなり分かりづらいです。
大まかな流れとしては、コストになるカードをたくさん引き、それを使ってカードをプレイ。たくさんカードを引くために生産や消費を行うといった感じです。カードをプレイすることで、アクションごとに追加でカードを引ける効果も増えていくため、拡大再生産の一面もあります。
日本語版が発売された当時、購入して何度かやってみたのですが、一緒に遊んだメンバーの反応が芳しくなく、手放してしまいました。今回、2版が発売されるということで、再び入手して、さっそくやってみたのですが、当時と同じような反応でした。
決して万人に勧められる感じではないです。
ただ、わたし自身はいろいろ経験を重ねたこともあり、当時よりもだいぶスムーズにルールが理解できました。10年前とは遊んでいるメンバーも違うため、今遊んでいる他の人たちがどういった反応を示すか期待です。
| タイトル | Race for the Galaxy |
|---|---|
| 発行年 | 2007年 |
| プレイ人数 | 2~4人 |
| プレイ時間 | 30~60分 |
| デザイナー | Thomas Lehmann |
| BGGリンク | Race for the Galaxy | BGG |