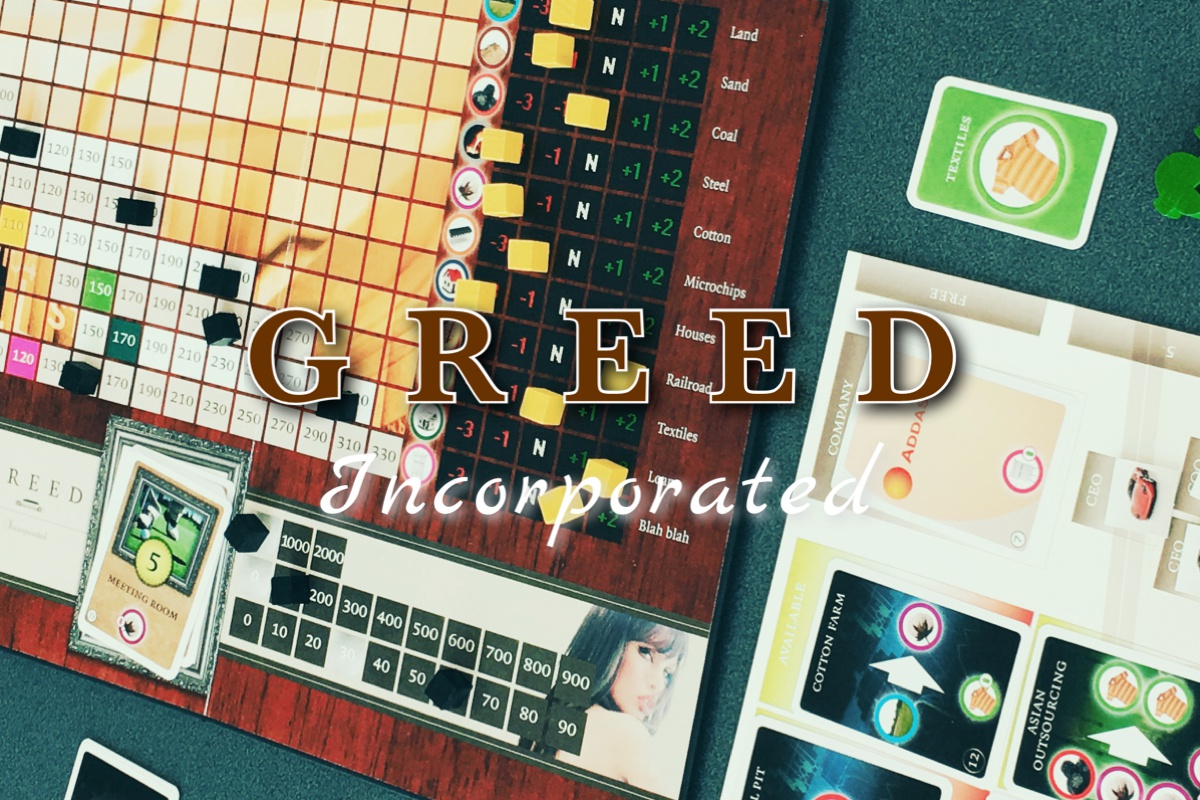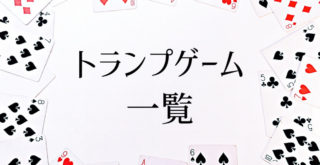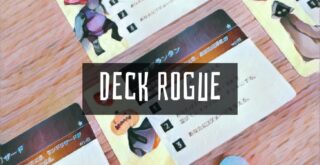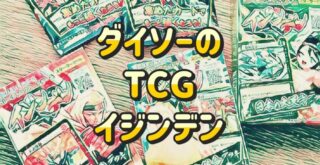「トラヤヌス」は、「ノートルダム」「ブルゴーニュ」「倉庫の街」などでお馴染みのシュテファン・フェルトの作品です。最近ではフェルトというと要素がてんこ盛りのイメージがありますが、トラヤヌスもそれにもれず、かなりの要素が詰め込まれています。
トラヤヌスについて
タイトルの通り、舞台はトラヤヌス帝が統治するローマ帝国です。
プレイヤーはさまざまなところに手を伸ばしながら己の権力を高めていきます。
手番に行えるアクションは6種類です。
- 海港
- 広場
- 軍事
- 元老院
- トラヤヌス
- 建設
それぞれのアクションの中でもいくつか分かれているため、細かく分けると12種類のアクションがあります。
この時点でなかなかのボリュームですが、それなりにボードゲームの経験があれば、戸惑うほどの量ではありません。

トラヤヌスのキモはこのアクションを選ぶための方法です。
プレイヤーには個人ボードがあり、その右半分に6つの皿のイラストと先ほど挙げた6種類のアクションが描かれています。
まず、この皿に6色×2の12個のコマを2つずつ分けて置きます。置く場所は自由で、同じ場所に同じ色を置いても構いません。
アクションを行う際は、その皿の中のいずれかを選び、そこにあるコマをすべて取ります。
取り出したコマを時計回りに隣の皿に1つずつ置いていき、最後にコマを置いたところのアクションを行います。
さらに皿の横にはトラヤヌスタイルが置かれています。
コマを置いてアクションを行う際、もしタイルに書かれた色のコマがその皿とそろっていればタイルを獲得することができます。
タイルを取得するためのコストは2つのコマですが、条件さえ満たしていれば、その皿にコマが3つ以上乗っていても構いません。
こうしてさまざまなアクションを駆使しながら得点を集め、4ラウンド終了時にもっとも得点が多いプレイヤーの勝利です。
やりたいアクションができない
多様な得点方法、独特な時間トラック、フェルトらしい減点など、とにかくいろいろな要素があるのですが、なんといってもアクションサークルが最大の特徴です。
伝統ゲームであるマンカラのようなシステムだということは聞いていたのですが、ここまで思い通りにできないものだとは思いませんでした。
このシステムの恐ろしいところは目先のことだけでなく、先々のことまで考えないと、選択肢がどんどん狭まってしまうことです。
「あ、あのタイル取れる!」と思ってアクションを行うと、次のターンでは「あのアクションしたいけどできない……」ということがよく起こります。
もちろんトラヤヌスタイルの取得を重視することもやり方としてありでしょうが、この「やりたいときにやりたいことができない」というのは、なかなか新鮮でした。
一般のゲームでは自分の手番では基本的にすべてのアクションが行えます。
ワーカープレイスメントならば、他の人にすでにそのアクションを行われてしまうとできないことはありますが、トラヤヌスでは自らの手で、自分のアクションを封じてしまいます。
「ここで軍事アクションすれば10点だ!……て、軍事アクションできないじゃないか!!」
これが何とももどかしくもあり、面白くもあります。
今まで、いろんなボードゲームをしてきたメンバーも「このゲーム考えたやつは頭がおかしい」「なんなんだよ、このゲームはっ」「これは変態だ……」とうれしい悲鳴を漏らしていました。
得点方法が多様で、タイルの配置にランダム要素があるので、遊ぶ度に新しい発見がありそうです。
しかし、1度やったくらいでは次どうすればいいのかの方針は思いつきませんね。
今回、全員が初プレイで4人で遊びましたが、ルール説明を含めてかかった時間は3時間弱でした。箱に書かれた目安時間は人数×30分なので確かに1度やれば2時間くらいかなという気はします。
ボードゲームの面白さでいえば相当なレベルです。
ただし、手放しで人に勧められるかというと、そこは難しいところです。要素の多さ、独特なシステムで最初は圧倒されるかもしれません。言語依存はないので、その辺りは遊びやすいですね。
| タイトル | Trajan |
|---|---|
| 発行年 | 2011年 |
| プレイ人数 | 2~4人 |
| プレイ時間 | 60~120分 |
| デザイナー | Stefan Feld |
| BGGリンク | Trajan | BGG |