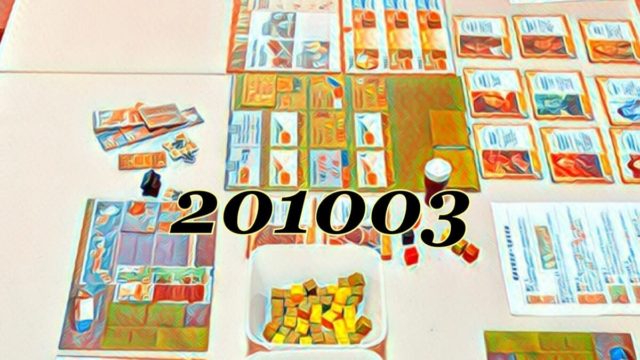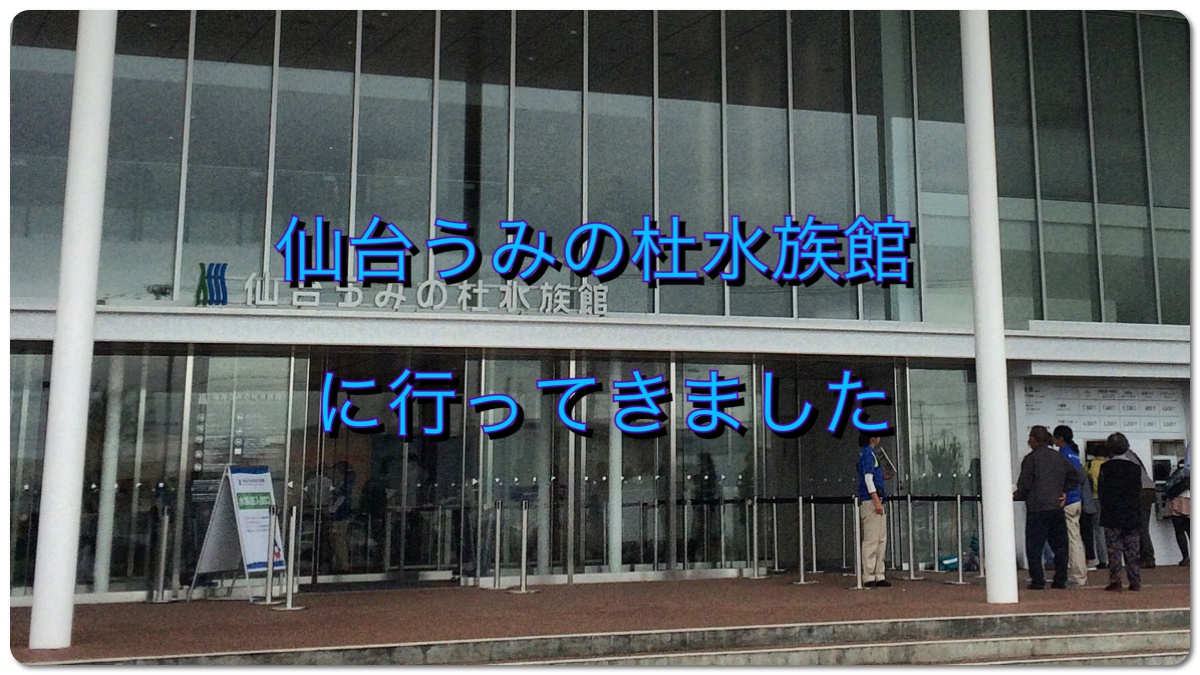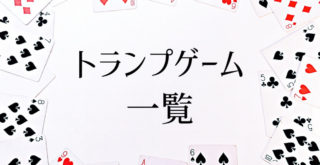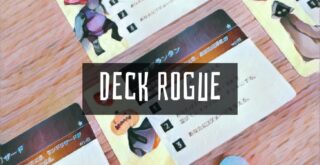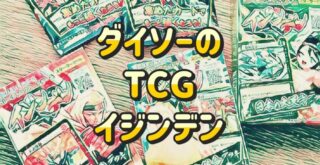人気のボードゲームデザイナーであるステファン・フェルトの作品です。
2015年09月に日本語版が発売予定です。
アクアスフィアについて
舞台は海底です。
そこでロボットにプログラミングをしたり、タコを退治したり、潜水艦を造ったりします。
プレイヤーのコマは技師とボットに分かれており、技師はプログラミングをしたり、アクションを行う場所を決定します。ボットは実際のアクションを行います。
手番にできることは3つあります。
プログラムの割り当て
ボットに対してプログラミングをします。
どのプログラムがなされるかは指令室の状況によって異なります。
プログラムの実行
入力されているプログラムを実行します。
パス
手番をパスします。
1度パスすると、そのラウンドはもうアクションできません。
アクアスフィアのキモとなっているのが、プログラムの割り当てと実行が別に行われるということです。やりたいアクションがすぐにできる訳ではなく、まずプログラムをして、後にアクションを実行するというタイムラグがあります。
しかも、選べるプログラムもしばりがあるため、こちらもかなり制限があり、好きなアクションを選べる訳ではありません。
このままならなさがアクアスフィアの醍醐味でもあります。
また、要素はかなり多めです。
コストを支払ってアクションを実行するエリアを移動したり、自分の研究室を拡張したり、得点をアップさせるためにクリスタルを取ったり、マイナス点を減らすためにタコを倒したりと、さまざまなことをバランスよく行っていく必要があります。
一応、個人ボードにできることや得点に関する情報は描いてあるのですが、それでもボードゲームに慣れていないと混乱するのではないでしょうか。
アクアスフィアの感想

初回でうまくやりきるのは、ほぼ無理かと思います。
しかし、やればやるほどいろいろなことが分かってきて、上達を実感できるゲームです。
研究室の拡張部分と開発カードはめくり運がありますが、そこまで運に左右されるゲームではありません。その場その場に応じた戦略が要求され、実力差が如実にでます。
また、細かい処理やできることが多いため、最初は「???」となります。けれどもやり始めるとだんだんとすべきことが分かってきます。この辺りはさすがですね。
ボードはカラフルなのですが、やっていることに派手さがないため、全体的に地味な印象が強いです。一気に大きく得点するのではなく、コツコツ得点していくタイプなので、その辺りも好みが分かれるでしょう。得点できる要素も多いので、すべてに気を配る必要もあります。
そろそろ日本語版が発売されますが、例によって言語依存はまったくありません。
すべてがアイコンで説明されており、書いてある文字は数字くらいです。
そのため、言語にこだわらず安い方を買うのがおすすめです。