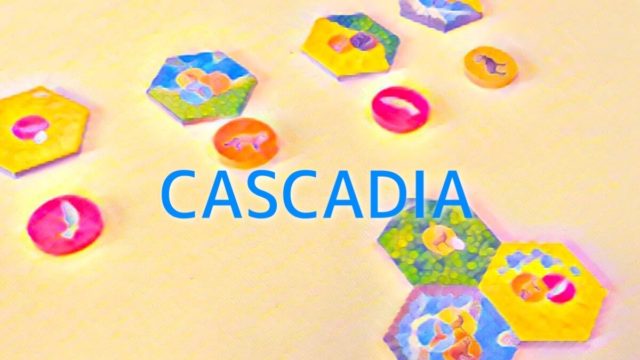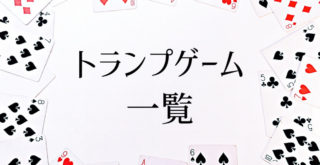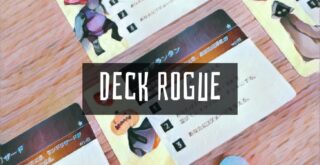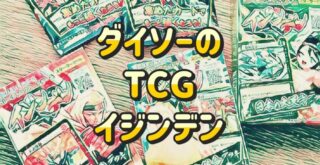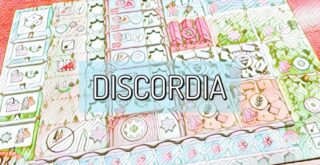「帝国の時代:インペリウム・クラシック」は新しいカードを獲得しながら自国を発展させていく1~4人用のゲームです。8種類のデッキが入っており、すべて構成が異なります。
帝国の時代:インペリウム・クラシックについて

自分の文明のデッキを受け取り、プレイの準備をします。初期資源として物資、人口、進歩のトークンを受け取ります。
市場ボードを並べサプライの準備を行います。
ゲームの流れ
ゲームは終了条件を満たすまでラウンドを繰り返します。
各プレイヤーが一手番ずつ行い、最後に至点の処理を行うとラウンド終了です。
手番で行うこと
手番では以下の3つのうち、いずれか1つを行ってから整理を行います。
- 発動
- 革新
- 反乱
発動
アクションの実行や消耗能力の使用を任意の順番で行います。
アクションを実行するたびにアクショントークンを失います。アクショントークンは3つあるため、3枚までアクション(カードのプレイ)が行えます。
場にある能力を使う場合は、消耗トークンをカードの上に置きます。こちらも5枚あるため、5つまで実行できます。
革新
アクションを実行せず、手札をすべて捨てます。
その後、「未開」「文明」「領地」「民衆」のいずれかの調達を行います。
反乱
アクションを実行せず、手札にある任意の枚数の不穏カードを不穏パイルに戻します。
整理
以下を順番に行います。
- 市場に進歩トークン1つを加える
- アクション・消耗トークンを取り除く
- 手札から任意の枚数を捨てる
- 手札上限までカードを引く
ドローデッキの再シャッフル
デッキがなくなり、なおかつカードを引かなければならない場合、デッキの再シャッフルを行います。現在の状態によって処理が異なります。
状態カードが蛮族の場合
国家デッキに消耗トークンが置かれてなければ国家デッキの一番上のカードを捨て札に加えて、消耗トークンを国家デッキの上に置きます。
国家デッキに消耗トークンが乗っているか、消耗トークンが状態カードにない場合、このステップは飛ばします。
このとき捨て札に●カードが置かれると状態カードが帝国になります。
それから捨て札をシャッフルして新たなドローデッキを作り、ドローの続きを行います。
消耗トークンは「整理」のタイミングで取り除かれます。つまりこの処理は連続でリシャッフルがかかることを防いでいます。通常は「デッキが枯れたら国家デッキから1枚捨て札に加える」という認識で問題ありません。
状態カードが帝国の場合
蛮族の時と同じような処理をしますが、発展カードはコストを支払わなければ捨て札に移動できません。
至点
全員が手番を終えるとラウンド終了になります。
次の手番を始める前にカードに書かれた至点の効果を解決します。
ゲームの終了
ゲームは得点か崩壊が発生した時点で終了します。
得点
以下のいずれかの条件を満たすと終了トリガーが引かれます。そのラウンドを最後まで行い、もう1ラウンド行ってゲーム終了です。
- メインデッキにカードが残っていない
- いずれかのプレイヤーが発展エリアのカードをすべて発展させた
- 王の中の王カードが裏向きになった
得点計算を行い、もっとも得点が多いプレイヤーの勝利です。
崩壊
不穏パイルに崩壊カードがなくなると崩壊が起こります。
アクションの途中であってもゲームが終了します。各プレイヤーは自分が所有する不穏カードの枚数を数え、もっとも枚数が少ないプレイヤーの勝利です。
間違えやすいポイント
進歩トークンは物資トークン・人口トークンの代わりに使える
ルールブックのキーワードの説明に書かれていますが、進歩トークンは物資トークンや人口トークンの代わりに使えます。
1進歩トークンは1人口または2物資として使えます。
この場合、お釣りは出ません。また、あくまでも代わりに支払うだけなので進歩トークンを他のトークンに変換することはできません。
取得・調達
「取得」と「調達」どちらも市場からカードを獲得するアクションですが、「調達」のほうが上位アクションとなっています。
「取得」の場合、不穏カードがあればそれも一緒に獲得しなければなりません。また獲得できるのは場にある対応するカードだけです。
「調達」の場合、不穏カードは取りません。また指定アイコンのカードがない場合、対応するデッキの一番上のカードを獲得できます。そのデッキが空の場合、メインデッキから対応するアイコンのカードが出るまでカードをめくれます。
この際、めくったカードはデッキに戻しリシャッフルします。もし該当アイコンのカードがない場合は進歩トークンを2枚もらいます。
放棄・追放
「放棄」は自分の場に出ているカードを捨て札にすることです。もし駐留しているカードがあれば、それも捨て札にします。
「追放」は市場ボードの隣にある追放パイルにカードを置くことです。いわゆるデッキ構築における「破棄」は「追放」に相当します。
文明系デッキ構築

「用語が多い」という評判は目にしていたのですが、確かに実際にやってみると、一度聞いただけですべて理解するのは無理でした。
似たような言葉でも処理が異なるため、何度も確認する必要があります。
今回は2人で遊び、ルール説明からプレイ終了まで3時間ほどでした。とにかく用語の確認に時間が取られるます。ただ、そこまで複雑でもないため1度最後まで通して遊べば次回はもっと短縮されそうです。
最初は何となく強そうなカードを獲得していけばいいのかなと思ってプレイしていたのですが、やっていくうちに「あー、こんな感じで進めればいいのか」とわかってきました。
ゲーム中、蛮族から帝国に変わるタイミングがあります。
そうすると蛮族のカードが使えなくなり、帝国のカードが使えるようになります。今まで強力だったカードが使えなくなることもあるため、歴史や追放などで上手く圧縮していかなければなりません。
今回は相手が発展カードをすべて発展させたところでゲーム終了となりました。
得点計算してみると、わたしだけが名声カードを獲得していたこともあり勝てました。ちなみに相手は名声カードに一切触れていなかったため、得点が高いことはわかっていなかったようです。
相手の物資を奪ったり、領土を破壊したり、不穏を押しつけたりといった直接的なインタラクションもありますが、基本的には自分の思う方向にデッキを組んでいくことになります。
ほとんどのカードがテキスト効果のため、初回は読み込むだけでも時間がかかります。文明によってカードの構成が違うこともあり、相手のカードまですべてを把握するのはかなり難しいです。
また初回は「駐留?」「歴史に置く?」となることは間違いないので、よく使う用語の一覧はあったほうが便利そうです。
デッキ構築や文明系のゲームが好きなので、かなり好印象でした。
ソロプレイの評価も高いので近々やってみようと思います。
| タイトル | Imperium: Classics |
|---|---|
| 発行年 | 2021年 |
| プレイ人数 | 1~4人 |
| プレイ時間 | 60~120分 |
| デザイナー | Nigel Buckle, Dávid Turczi |
| BGGリンク | Imperium: Classics | BGG |