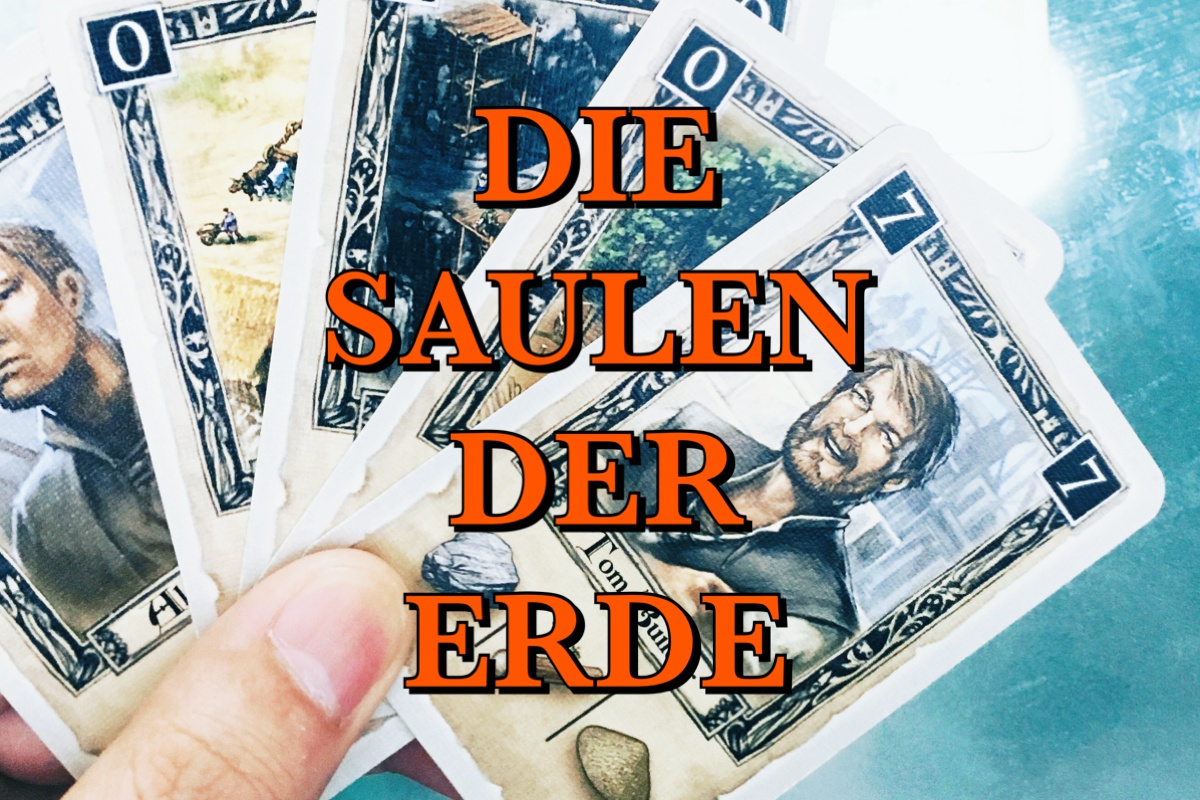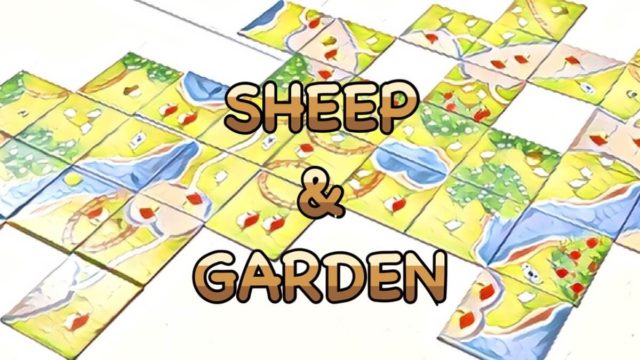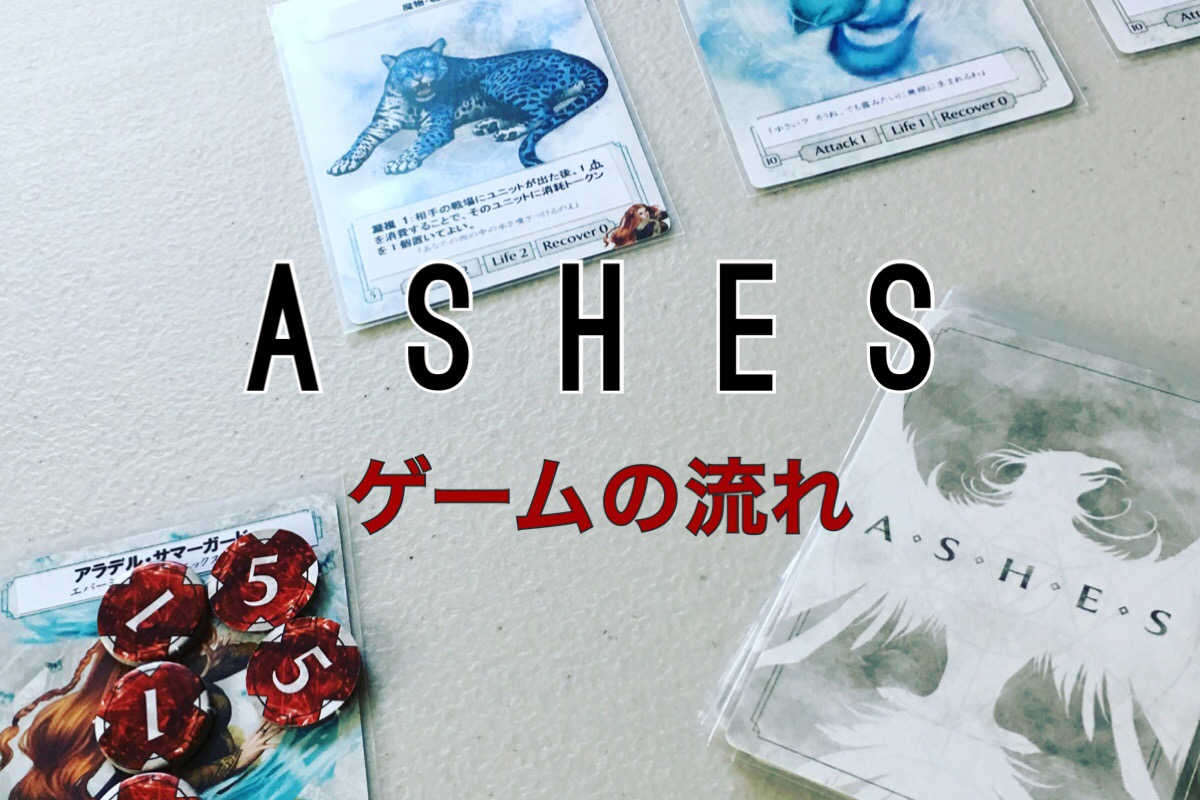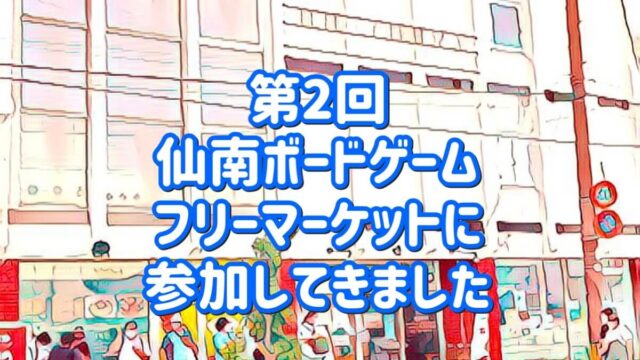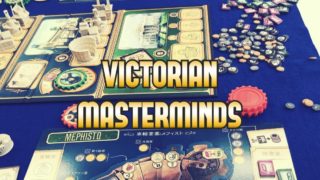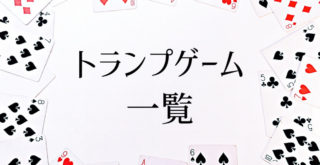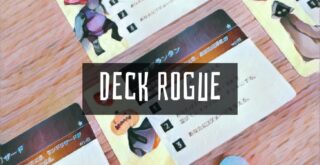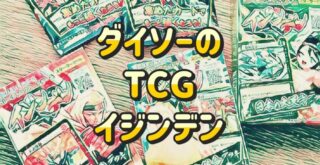2019年ゲームマーケット春の新作、狩猟の時代を4人で遊びました。さまざまな要素がコンパクトにまとまっており、とても遊びやすいワーカープレイスメントでした。
狩猟の時代

Twitterで好評の声をいくつも見かけたので、気になっていたゲームです。通販で買えるようになっていたので、さっそく購入して遊んでみました。
個人ボードありのワーカープレイスメントで、アクションスペースにコマを置いたときと、手元に戻したときにアクションが発動します。
それぞれの狩場カードにアクションスペースが描かれているのですが、右に行くほどアクションが強力になっていきます。あとからコマを置く場合は、すでにあるコマは右に移動するので、コマを置いておくとだんだんと効果が強まっていきます。
この辺りはツォルキンと似ているのですが、狩猟の時代の場合、他の人が手元に戻すことで、自分のコマもまた左に戻っていくので、上手くタイミングを見計らないと結局もとのアクションに戻ってしまいます。
また、個人ボードから小屋や部下といったコマを取り除くことで、得点が出てきたりするのはテラミスティカを思わせます。
さまざまな要素がコンパクトにまとまっており、なおかつプレイ時間もそれほどかからないので初めてワーカープレイスメントを遊ぶという場合にもちょうどよさそうです。
狩場カードの種類が豊富で、組み合わせによってプレイングが大きく変わってきそうなのもリプレイ欲が湧きますね。
大聖堂カードゲーム

各自がカードを1枚ずつ出していて勝敗を決する、いわゆるトリックテイキング形式のゲームなのですが、判定がかなり独特です。
まずフォローの概念がないので、好きなカードを出すことができます。そういったゲームはメイフォローとしていくつもあるのですが、カードを獲得するのはもっとも大きな数字のカードの色のプレイヤーというのが変わっています。
そのため、カードを出した人とカードを獲得する人が別になります。
しかも、次のリードはカードを出した人なので、初めは混乱しがちです。
さらに獲得したカードがそのまま点数になるわけでなく、資源と得点化するカードを別々に入手する必要があります。
その上、テキスト効果のあるカードも存在したりと、かなりクセが強いゲームです。
カードを出しても、自分が取れる訳ではないのでコントロールはほとんど効きません。手札に自分の色がなかったりすると、相手にマイナス点を差し込んでやるくらいで精一杯です。
このままならなさで不思議な面白さがあるのが、また独特です。